種類
構造、材質
口金
アダプター
空気入れホルダー
仏式バルブの空気入れ方
標準空気圧
最大圧力計算器
加圧能力
引力計算器
空気入れはタイヤのチューブに加圧空気を入れる器具で、空気入れの口金(接続口)をチューブのバルブ(弁)に接続して空気を入れる。バルブには英式(主にシティ車用)、仏式(主にロード車用)および米式(主にマウンテンバイク用)の3種類があるので、空気入れの口金はバルブ(弁)の種類に合ったものを使う。
種類
広義の空気入れには次のような種類がある。大きく分けて定置空気入れ及び運搬空気入れに分類できる。人力によらない空気入れは、技術上インフレーターと呼ばれる。
床置き空気入れ
フレーム空気入れ
ミニ空気入れ
緩衝器空気入れ
CO2インフレーター
足踏み空気入れ
引き綱空気入れ
タイヤインフレーター
公共空気入れ
シートポスト空気入れ
空気圧縮機
床置き空気入れ




床に置いて使う空気入れ。最も一般的な常用の空気入れであり、使用頻度は他の空気入れに比べてはるかに多い必需品。足置きが付いていて、足を載せて床に固定してハンドルを上下させて空気を入れる。足置きは折りたたみできるものもある。
圧力計が付いている形式が望ましい。圧力計が上部に付いている形式は、圧力が見やすい。独立の圧力計もある。仏式弁(プレスタ弁)及び米式弁(シュレーダー弁)の口金が付いた形および2つの口金を付け替える形などがある。シティ車に使われている英式弁(ウッズ弁)に対応する接続口金の付いた空気入れが圧倒的に多い。英式弁は圧力測定ができないので空気入れに圧力計は付いていない。出来れば乾燥した日に空気を入れることが望ましい。
大容量又は高圧の2つのモードをハンドルのスイッチで選択できる形もある。無圧状態から空気を入れるときは、大容量モードで入れて圧力が高くなると高圧モードに切り替えて入れることもできる。
握りを押して空気を入れている時に、粗悪な樹脂製の握りが折れて負傷した事例が報告されている
握りの中心から左右それぞれ50mm離れた位置に合計1,470Nの荷重を1分間加えたとき、破損してはならない(「JIS D9455 自転車用空気ポンプ」)。
フレーム空気入れ







概要
フレームのポンプペグ(掛け具)または空気入れホルダーに取り付けて持ち運ぶ空気入れ。フレームポンプ及び携帯ポンプとも言う。
種類
ペグ取付型は、ポンプペグ間に挟んで取り付けるための圧縮コイルばねを内蔵している。
サイズ
ペグに付けるこの空気入れのサイズは、取り付けるペグ間の距離で表す。長さは500mm前後。スリーブを動かすことにより、ペグ間距離に合わせて長さを調節できる形がある。
仕様
ホルダー取付型は、空気入れホルダーを付属しているものもある。空気入れを押す取っ手は、軸上で円筒状のものとノブ状のものがある。床または道に置いて、床置き空気入れとして使えるようにした形式もある。胴(シリンダー)の材質は、軽量化のためアルミ合金製が多い。質量は100~300g。
ポンプペグ
フレームに2個付けてフレーム空気入れを挟んで取付けるための掛け具。ペグはフレームの上管(トップチューブ)下部(ダウンチューブ)、立管(シートチューブ)または下管にロウ付け又は溶接されている。バンドでフレームに固定するペグもある。ペグは掛け具のこと。フレーム空気入れは、ペグ間距離に合ったサイズを選定する。フレーム空気入れには、ペグ間に挟んで取り付けるためのばねを内蔵している。
空気抵抗
上管(トップチューブ)の下に付けると、立管(シートチューブ)に付けるよりも、高速での空気抵抗は約0.8%少ない。
ミニ空気入れ







概要
フレーム空気入れより短く軽い空気入れ。フレーム空気入れより空気を入れる時間がかかる。非常用の空気入れと見なしてよい。
大きさ
全長は100~290mm。ジャージーのポケットに入るものもある。短いとハンドルを押す回数は多くなる。
質量
50~170g。
接続
バルブとの接続方法は、手でバルブに押し付けておく形及びバルブにねじ込む形がある。
特殊仕様
(1) マウンテンバイク専用の形がある。
(2) 仏式バルブ及び米式バルブのいずれにも対応できる形がある。
(3) アダプターを付けているものがある。
(4) Tハンドルになるものもある。
(5) 小さい圧力計の付いた形がある。
(6) バルブが汚れないようバルブカバーの付いたものがある。
(7) フレームへの固定具が付属しているものもある。
(8) 竹製のにぎりが付いているものもある(下図)。

(9) 本体を握ったときに滑らないよう、本体にゴム製の握り部を付けた形がある。
(10) 押し及び引きいずれにおいても空気が入るようになっている形式(往復空気入れ)がある。
(11) ホースが付属している形がある。
(12) バルブを傷めずかつ操作し易いよう、内蔵したホースを引き出して90°曲げて使う形がある(下図の黄色の矢印)。

ホルダー
ポンプをフレームに取付けるための空気入れホルダー(保持器)がある。
材質
本体材質はアルミ合金、炭素繊維強化樹脂(CFRP、俗に言うカーボン)およびABS樹脂など。
緩衝器空気入れ




空気ばね式のサスペンション(緩衝器)は空気圧を変えることにより予荷重を変えて、沈みを設定するようになっている。その空気圧の設定に使う。高圧(最大2,000~2,500kPa)、小容量となっている。圧力計が付いていることが必要。空気圧を微調整するために空気抜き弁が付いたものが多い。 前輪用と後輪用の緩衝器は圧力が異なる。サスペンション空気入れとも呼ばれる。
CO2インフレーター
 手の平に乗るほど小さい容器に加圧充填したCO2(炭酸ガス)を空気の替わりに使う。タイヤをほとんど瞬間的に加圧することができる。 主に、緊急の携帯用として使用するのが一般的。容器1本で、1本または2本のタイヤを加圧できる容量を持っている。容量はCO2の質量(12g、16gなど)で表されている。 加圧できる最高圧力は、メーカーにもよるが、300kPa、500kPaおよび1000kPaなど。
手の平に乗るほど小さい容器に加圧充填したCO2(炭酸ガス)を空気の替わりに使う。タイヤをほとんど瞬間的に加圧することができる。 主に、緊急の携帯用として使用するのが一般的。容器1本で、1本または2本のタイヤを加圧できる容量を持っている。容量はCO2の質量(12g、16gなど)で表されている。 加圧できる最高圧力は、メーカーにもよるが、300kPa、500kPaおよび1000kPaなど。
参考: CO2インフレーター
足踏み空気入れ





床において足で踏んで空気を入れる空気入れ。レバーを介してピストン棒を押す形および直接ピストン棒を押す形がある。シリンダーが1筒の形(シングルバレル)および2筒の形(ダブルバレル)がある。フットポンプともいう。
引き綱空気入れ

空気入れを足で抑えて、引き綱の取っ手を上に引上げると本体内部のプーリが回り、それに付いたクランクがピストンを左右に動かし空気を左右に押し出す複動式の空気入れ。 空気容積の大きいマウンテンバイクのタイヤに向いている。接続金具、ホース、綱(コード)及び取っ手は本体に納まり、大きさは片手ほど。圧力計が付いている。
タイヤインフレーター



電動の空気入れ。人力によらない空気入れは、技術上インフレーターと呼ばれる。主に自動車およびオートバイの電源を利用してタイヤの空気入れとして使われることがある。バッテリーを内蔵した形もある。電圧12Vの電動機(モーター)で圧縮機を回して、圧縮空気を作る。圧力計が付いている。付属のホースでタイヤ(チューブ)のバルブに接続する。外観はメーカーによって大きく異なる。騒音が問題になるものもある。自転車タイヤの空気入れとしても使えるが、手押し空気入れで間に合うので、ほとんど使われない。本体の長さは140~240mm。
公共空気入れ





公共の駐輪場などに設置する床置き空気入れ。稀に、自転車店が店先に設置することがある(右端図)。移動及び盗難の防止のために床に3本のアンカーボルトで固定するようになっている。圧力計の付いた形がある。駐輪場空気入れとも言う。
シートポスト空気入れ


サドル支柱(シートポスト)、サドル及び床置き空気入れを一体にした空気入れ。使うときは立管(シートチューブ)からサドルと共に抜き出す。サドルを空気入れハンドルとして使う。商品名はポストポンプ。
空気圧縮機

ガソリンスタンドなどにおいて、容量の大きい自動車タイヤなどに空気を入れるための圧縮空気発生機。シリンダーに吸気した空気(大気)をピストンで圧縮し、吐出した圧縮空気は圧縮機および電動機が乗った円筒形の圧力容器に貯える。容器の空気圧力が設定値になれば電動機は自動的に停止する。容量の少ない自転車(マウンテンバイク)のタイヤに空気を入れる場合は、入れすぎてパンクすることがあるので要注意。
構造、材質

空気入れを構成する主要部品は、胴(シリンダー)、ピストン、ピストン棒およびハンドルである。
ピストン棒の上部に付いているハンドルを押すと、胴の中でピストン棒の下部に付いているピストンが下に押されて空気を圧縮する。圧縮された空気は、ホースと口金(チャック)を通って接続したバルブ(弁)からタイヤのチューブに入る。胴の空気出口に逆止弁の付いたものもある。圧力計が付いたものもある。ただし、英式弁の付いたチューブは、その弁の構造上圧力測定はできない。胴の材質はアルミ合金が多い。軽量化のためにCFRP(炭素繊維強化樹脂)を使っているものもある。
口金





空気入れのホースの先端に付いていて、タイヤ(チューブ)のバルブ(弁)と接続するための金具は口金と呼ばれる。使用しているバルブ(弁)に合った形を使う。Aは仏式弁用、Bは米式弁用、Cは米式弁用と仏式弁用を合体させていずれも使えるようにしたもの、そしてDとEは仏式弁用および米式弁用の接続口を設け共用としたもの。いずれも一例。低い圧力へ圧力調整ができるよう、排気弁を付けた形もある。
アダプター
バルブ(弁)に付けて、型式の異なる空気入れが接続できるようにした金具。バルブ(弁)は3種類(英式、仏式および米式)があり、接続口に互換性が無いので専用の空気入れが必要。アダプターをバルブに付けることにより、異種の空気入れが使える。次の4種のアダプターがある。空気を入れた後にアダプターは外す。
- (A) 英式V→米式P

- 英式弁(ウッズバルブ)に付けて、米式弁用の空気入れが接続できるようにするアダプター。
- (B) 米式V→英式P

- 米式弁(シュレーダーバルブ)に付けて、英式弁用の空気入れが接続できるようにするアダプター。
- (C) 仏式V→米式P

- 仏式弁(プレスタバルブ)に付けて、米式バルブ用の空気入れが接続できるようにするアダプター。使用に当たっては、仏式バルブの丸ナット(ロックナット)を上端まで緩めて、丸ナットの上端を押すことにより弁棒を下げて空気が弁座を通過できるようにして、仏式アダプターをねじ込み、空気入れで空気を入れる。 仏式アダプターを外し、丸ナットを元の位置まで締めてバルブから空気が漏れないようにする。
- (D) 米式V→仏式P

- 米式弁(シュレーダーバルブ)に付けて、仏式弁用の空気入れが接続できるようにするアダプター。
空気入れホルダー




空気入れをフレームに取付けるための保持器。空気入れマウント又は空気入れハンガーともいう。
ボトルケージのダボにねじで取付ける形がある。フレームに当てるブロック及びバンドで取付ける形がある。ボトルケージとホルダー(バンド)が一体になった形もある。
仏式バルブの空気入れ方
仏式バルブは他のバルブと空気の入れ方が少し違うので、一般的な入れ方を次に示す。
- バルブのキャップを外す。
- バルブの先端の丸ナットを回して、最後まで緩める。
- 丸ナットを指で押すことによって、弁体が弁座に固着している場合は剥がす。押して空気が漏れれば問題ない。
- 空気入れの口金が米式バルブ用の場合は、アダプターをバルブステムにかぶせ、指の力で止まるまでねじ込む。
- 空気入れの口金をアダプターにあてて、所定空気圧まで空気を入れる。
- アダプターを使った場合は、それを外す。
- 丸ナットを最後まで締める。そうしないと、空気が少しずつ漏れることがある。
- キャップをかぶせる。ただし、キャップは必ずしも必要ない。
標準空気圧
タイヤに空気を入れるには、自分と自転車に合った空気圧を知る必要がある。標準空気圧はタイヤの右側面に刻印されている。ロード車の標準空気圧は500kPa(700x32C)、600kPa(700x28C)および700kPa(700x25C)でマウンテンバイクやシティ車の標準空気圧(多くは300kPa)より大きい。
参考: タイヤ緒元(標準空気圧)
最大圧力計算器
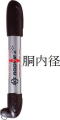 手押しの空気入れでタイヤ(チューブ)に入れることのできる最大圧力を計算する計算器です。押す力が大きいほどそして空気入れの内径が小さいほど、最大圧力は大きくなる。マウンテンバイクよりロード系のタイヤが大きな圧力を必要とする。圧力が同じ場合は胴内径が小さいほど軽く押すことができるが、押す回数は増える。
手押しの空気入れでタイヤ(チューブ)に入れることのできる最大圧力を計算する計算器です。押す力が大きいほどそして空気入れの内径が小さいほど、最大圧力は大きくなる。マウンテンバイクよりロード系のタイヤが大きな圧力を必要とする。圧力が同じ場合は胴内径が小さいほど軽く押すことができるが、押す回数は増える。
- 計算例
- 押す力が400N(ニュートン)そして空気入れ胴(シリンダー)内径が28mmの場合、タイヤに入れることのできる最大圧力は650kPaとなる。
加圧能力
JIS D9455(自転車用空気ポンプ)に規定のある空気入れの空気加圧能力を表1に示す。 同表のシリンダー内径は胴内径のこと。
(表が見切れる場合は横にスクロールできます)
| 種類 | 加圧能力 [kPa] | シリンダー内径 [mm] | 操作力(参考) [N] |
|---|---|---|---|
| フレーム空気入れ (フレームポンプ) |
295 以上 | 20未満 | 150 |
| 20以上 25未満 | 200 | ||
| 25以上 30未満 | 250 | ||
| 床置き空気入れ (フートポンプ) |
490 以上 | 30未満 | 400 |
| 30以上 35未満 | 550 | ||
| 35以上 40未満 | 700 |
引力計算器
物体に働く引力の計算器です。これは日本の平均引力で、引力は場所によって変わります。床置き空気入れに加えることの出来る最大力は、全体重を空気入れの握りかけた時の人体への地球の引力。力(引力も力の一種)の単位は万有引力を発見したニュートンに敬意を表して、ニュートンという単位が使われる。
- 計算例
- 体重60kgの身体に働く引力は、589Nとなる。

![[サンティック] 春夏用 メンズ サイクルパンツ](https://jitetan.com/home/wp-content/uploads/2025/04/image2025042212011600.png)
![[冒険倶楽部] ポケット工房40 F-40](https://jitetan.com/home/wp-content/uploads/2025/04/image2025042212012400.png)